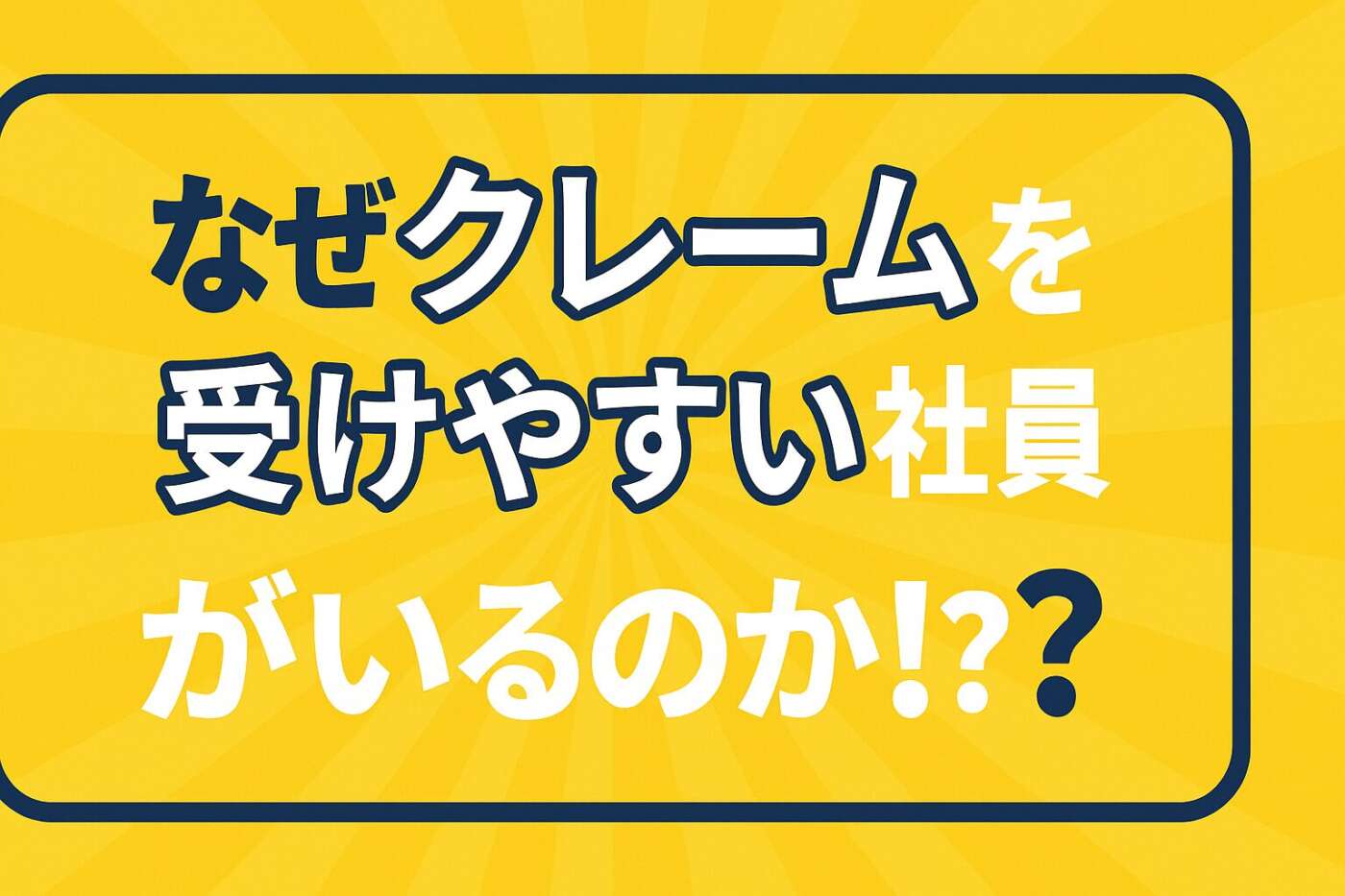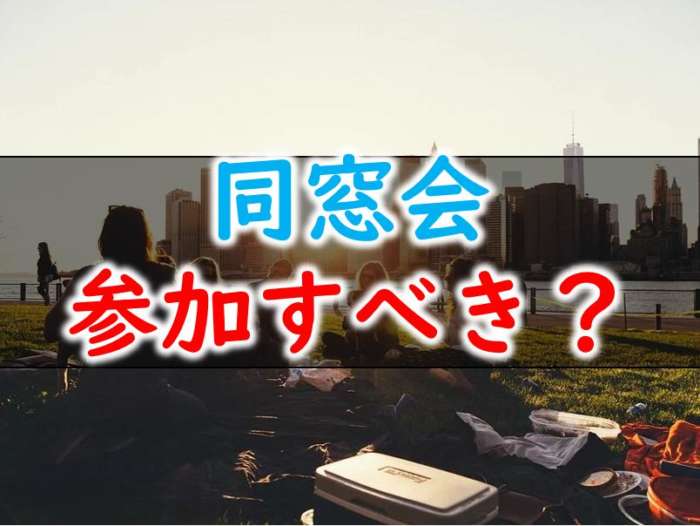人は本来、自ら成長したいと思うものです。
しかし、成長はある日突然訪れる・・・
というより、じわりじわりとやってきます。
そうすると、自分が成長しているかどうかわからない。
たとえば、初めて車の運転を学ぶ。
はじめはおっかなびっくりだけど、だんだん無意識にできるようになる。
すると、気が付けばかつてビビってた、縦列駐車も普通にできるようになったりします。
面白いことに、人間って、できるようになったことには関心がなくなる。
車を上手に乗りこなせるようになったけど、
「成長したなぁ、おれ」
と思うことはまれです。
そういう意味で、いろんなことができるようになっている。
だけど、成長を実感していないことも多い。
だから、年に一度、できれば月に一度くらいは、できるようになったことを棚卸することをお勧めします。
そうすると、この1年、この1か月が無駄ではなかったことに気づきます。
一方で、一向に成長しない部分もあるんじゃないでしょうか。
何かができるといったスキルというより、人の器という部分。
たとえば、部下が「思う通りに動かない」という状態。
今も、10年前も変わりがない、ってこと、ありませんか?
そこには理由があります。
それは、部下が動かない理由を、部下のせいにしているのです。
ハッキリ言って、責任転嫁です。
自分には責任がない、部下の問題である。
こう思っているうちは、問題は解決に向かわないし、私たちも成長しない。
じゃあどうすればいいか、といえば、私たちができる「行動を選択する」ということにフォーカスするのです。
「部下が期待した行動をしてくれない」という場合、原因はいくつかあると思います。
あなたの期待値を、部下が理解していないのかもしれない。
そもそも部下が、あなたに対して敬意を払っていないのかもしれない。
あるいは部下はびくびくしていて、必要以上のことをやらないようにしているのかもしれない。
こういう場合、往々にして、部下に考えさせる機会を持たせず、自分で答えを押し付けていることも多い。
いつもこちらが先回りしてるから、部下は思考停止してしまう、ということはよくある話です。
人と人の関係性において、どちらかが一方的に悪いというのはめったにありません。
基本的には、こちらの働き掛けに相手は反応し、相手の働き掛けにこちらが反応するという流れがあります。
となると、自分の反応を変えれば、相手の行動が変わることが予想されます。
後はいろんなパターンを試行錯誤するなかで、それなりの答えに近づけるのではないかと思います。
つまり、パターン化した応対をしている以上、双方の関係性は変わりません。
それを、自分が何をすべきか?ととらえるのと、相手はこうあるべき、ととらえるのでは結果に雲泥の差ができてしまいます。
相手が今のような反応をするには、そうする理由があるはずなのです。
こういった反応は、NLPを学ぶことでずいぶん理解しやすくなります。
そうすると何気ない部下とのやり取りの問題が、「ああ、そういうことか」と合点がいくことも何度もありました。
心理学は、ビジネスにおいては今や必須科目です。

28歳の時保険代理店業で起業し、保険会社の年間表彰に5年連続で選ばれる会社に育てる。
そのすぐ後、スタッフの半分が一気に会社を辞める事態になり「自分を変えなければ」と発起しNLPや心理学を本気で学ぶ。
『過去と他人は変えられないが、自分と未来は変えられる』ことを知り、全国の経営者やビジネスパーソンにもそれを伝えるため、セミナー活動や研修活動をしている。
【保持資格】
全米NLP トレーナー・LABプロファイル®トレーナー
交流分析士・心理カウンセラー・行動心理士