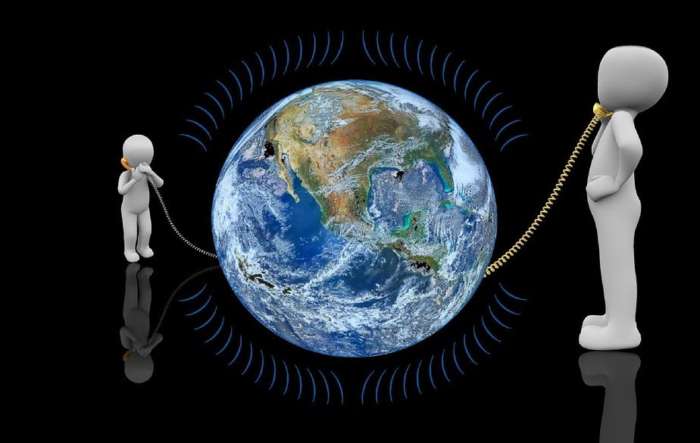「給料日まで1週間あるのに貯金がない」
「つい衝動買いをしてしまう」
「クレジットカードの限度額がもうない」
こんな人は普段からお金を散財しているかもしれません。
お金が手元から減っていくと、どんどん精神が疲弊してしまい、幸福感も下がってしまいます。
できることなら、散財癖は直したほうがいいでしょう。
こちらの記事では、散財してしまう人の心理・特徴やお金を散財してしまう理由について触れながら、解消法についても解説していきます。
散財してしまう人の心理・特徴3選

散財してしまう人の心理状態や特徴について紹介します。
当てはまるという方は注意してお金を使っていくようにしましょう。
劣等感が強く自信がない
普段から人と比べて、劣等感を感じている人は要注意です。
自分に自信がないと、モノに頼ってしまうので、どんどん買い物してしまいます。
高価なものを身に付けることによって、自分の価値が上がったように錯覚してしまうのです。
ですが、人間の欲求は底知れないので、高いものを買っても満足することなく、もっと高価なものに手を出してしまいます。
このループから抜けだすためには、根本的に自信をつけなければなりません。
他人と比較する癖を直して、ありのままの自分と向き合っていきましょう。
他人と比較して劣等感を感じた時の対処方法!他人と比較しないのは無理?
虚栄心が強い
虚栄心が強い人は、「人から良く思われたい!」という承認欲求が強いので人に奢ることが多いのでお金が無くなっていきます。
また、承認欲求が強いことから、高いものを買う癖が身についている可能性があります。
見栄を張っても身を滅ぼすだけなので、身の丈に合った買い物をしましょう。
本当に人から認められたいのであれば、読書やセミナーなど自己投資に使って、知識やスキルを磨いていくのが最も良い方法です。
外見ではなく、中身から磨くことで、お金を使う時間を減らし、学びの時間を増やすことができるのでお金が貯まっていくはずです。
外交的な人
ある研究では、内向的な人と外交的な人とでは、外交的な人のほうが散財癖が強い傾向にあったと言います。
しかも、外交的な人だとお金がない時こそ、他の人にお金がないとさとられたくないので、どんどんお金を使ってしまうという悲惨な状況に陥りやすいのだとか。
散財が散財を呼んでしまうのです。
素直に「お金がない」と伝えることに恐れを感じる傾向があるので、貧乏を隠すためにお金を使い、さらにお金を使ってしまいます。
外交的な人は借金を抱え始めたら、もっと借金してしまうリスクが非常に高いのです。
自分のことを外交的だと自覚のある人は、このことを肝に銘じて、財布のひもをぎゅっとしめてくださいね。
お金を散財してしまう理由

特に必要なものでもないのにお金を散財している時はストレス過多状態にあるのかもしれません。
ストレス社会と言われるほど、日本はストレスをためやすい環境にあります。
その理由としては、組織で動くことが美徳とされ、個人の主張をするのはあまり良くないとされる慣習が潜在的に持っているためだと思われます。
人は自分の意見を話せないでいると、ストレスをためこんでしまうので、どこかでストレスを解放するためのコミュニケーションの場がなければ、お金を発散させてしまうのです。
つまり、散財はストレス発散のためにとっている行動だと言えます。
ですが、ストレス発散のためにしていることなのに、お金が手元からどんどんなくなっていく現実と向き合うことになるので、皮肉なことにどんどんストレスを抱えてしまうのです。
この最悪なループから抜け出すためには、ストレスと上手に付き合い、お金を使わないで発散させる方法を取り入れていく必要があります。
お金を使わないでできるストレス発散方法

お金を使わないでストレスを発散する方法は気軽にできます。
あまり派手な事ではないので、見栄っ張りな人は慣れるまでは時間がかかるかもしれませんが、辛抱強くやって習慣化していくといいでしょう。
楽しいことがない時にストレスを軽減する方法!仕事が忙しい社会人におすすめ
軽く運動する
軽く運動すると血行が良くなり、体が軽くなります。
体と精神は繋がっているので、体が軽くなると心も軽くなってきます。
いつも窮屈さを感じているのでしたら、体を動かしてほぐしていくのがオススメです。
本腰を入れてスポーツをすると、どうしてもお金を使ってしまうので、軽いジョギングや筋トレがいいでしょう。
体をほぐす目的を忘れなければ、無駄なお金を使うことなく、運動を楽しめるはずです。
散歩する
運動にハードルの高さを感じるのでしたら、散歩がとても効果的なのでオススメです。
特に朝に散歩すると、朝日を浴びることでセロトニンが脳内で分泌され、睡眠の質も高めてくれるので、ストレスを抱えにくい体になります。
睡眠の質は人生の質です。
散歩の習慣を取り入れるだけで、人生が大きく好転すると言っても過言ではありません。
読書
読書もオススメです。
なぜなら、人間は知識の動物であり、新しい知識が蓄積されていくと喜びを感じるものだからです。
それに知識が蓄積されていけば、自制心も高まり、お金の散財癖が治る可能性も十分にあります。
一日のどこかで読書をする時間を作ってください。
特に、夜寝る前にインプット作業をすると、知識の定着に効果的だと言われているので、入浴中や就寝前にリラックスしながら読書するのはオススメです。
それでも散財してしまうなら

お金を使う事が癖になっているのなら、周りの人に助けを求めることが大切になってきます。
家族や友人に頼んでクレジットカードや通帳を預けるという方法もあります。
このようにすることで、無駄にお金を使うことを防ぐことができます。
継続していくうちに浪費癖が直り、お金を使わないでも人生楽しく生きられることに気付けるはずです。
もし、お金を預けることに抵抗があるのなら、根本的な考え方から変える必要があります。
本気で散財癖を直したいと思うのであれば、心理学セミナーを受講してみてはいかがでしょうか?
心理学の中でも特にNLPは心理学を実践に移すことに特化しているので効果を実感できることでしょう。
ぽるとでは定期的にNLPのセミナーを実施しています。
本気で変わりたいという方は、一度セミナーページをご覧になって会場まで足を運んでみてください。
LINE登録していただくとまさかの相談が無料で出来ます。

28歳の時保険代理店業で起業し、保険会社の年間表彰に5年連続で選ばれる会社に育てる。
そのすぐ後、スタッフの半分が一気に会社を辞める事態になり「自分を変えなければ」と発起しNLPや心理学を本気で学ぶ。
『過去と他人は変えられないが、自分と未来は変えられる』ことを知り、全国の経営者やビジネスパーソンにもそれを伝えるため、セミナー活動や研修活動をしている。
【保持資格】
全米NLP トレーナー・LABプロファイル®トレーナー
交流分析士・心理カウンセラー・行動心理士