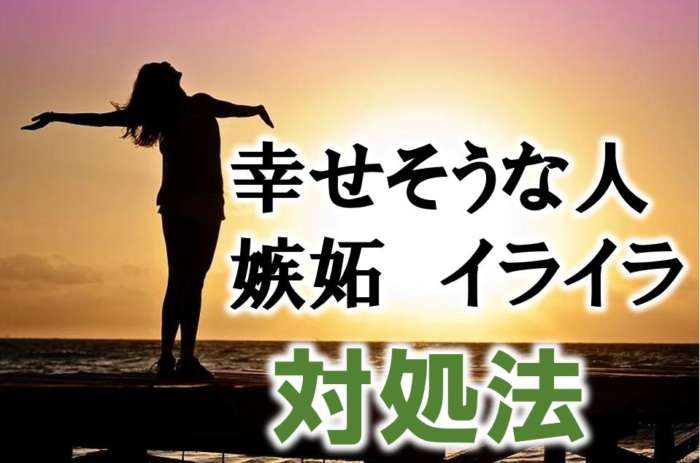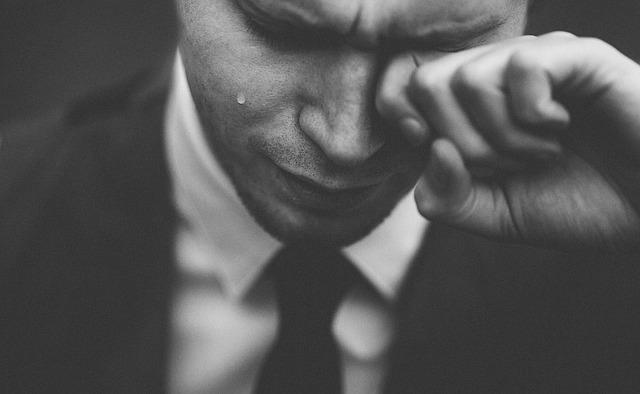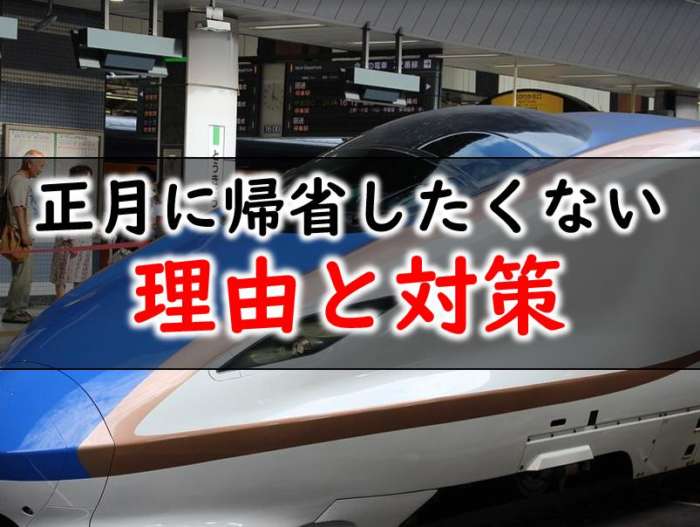「一致団結すれば百人力!」
「1+1は2ではない、3だ!」
そんなセリフ、よくありますね。
ここで残念なお知らせがあります。
人は集団になると、力が発揮できない生き物なのです。
その証拠になりそうな、2つの心理実験をご紹介しましょう。
一つ目は、リンゲルマン効果、社会的手抜きなどと言われるもののもとになる実験です。
1人でロープを全力で引いてもらいました。
結果として、63キロの力が加わりました。
3人になると、一人当たり53キロ、
8人になると、一人当たり31キロ。
つまり、一人当たりの力は、人が増えるほど力は小さくなっていきます。
単純に考えると、ロープを引く環境や状況によって、力が入りやすかったり、入りにくかったりがあります。そういった要素を排除するため、別の実験車による実験が行われたそうですが、結果の傾向はほぼ同じでした。
人は、集団になると、無意識に手抜きをするようだ、というのがこの実験の結論です。
もう一つの実験は、困った人を助けるか否か。
道端で具合の悪い人を見かけたとき、
自分一人が通りかかった場合、85%の人はその人を救助しました。
通行者が5人以上で実験すると、35%まで減りました。
傍観者効果と呼ばれるこの傾向は、自分でなくてもだれかやるという考えから助ける人が減ったと言われています。
誰かがやる。
こうやって、責任を”無意識に”逃れるのが人間の傾向。
この集団がどんどん大きくなると、無責任体質が目立ってきます。
それを律するため、大企業は社員を管理する。
ルールで縛り付けることで、辛うじて秩序を保とうとしているのかもしれません。
しかし、ルール、つまり強制は人のモチベーションを奪います。
ここをどうバランスをとっていくかが、リーダーとしての難しいことろだと思います。
方法の一つは、集団の中にいる、個人の役割を明確にすること。
プロジェクト全体はチームで回るわけですが、そのうちのどの部分を誰がやる、というのを明確にするのが重要です。意外とここが明確になっていないチームは多いように思います。
誰がトスを上げて、誰がスパイクを打つのか。
スポーツの場合はそこが明確です。
しかし、ビジネスにおいてはそれが曖昧なことが多く、全員にオールラウンドプレイヤーである事を求められがちです。
ここを得意な部分と、そうでない部分を社内で明確にし、それぞれが担うべき役割を明確化していく事は社内のモチベーションマネジメントには欠かせない要素だと思います。
あなたのチームのAさん。
彼が、彼女が、果たすべき責任は何ですか?

28歳の時保険代理店業で起業し、保険会社の年間表彰に5年連続で選ばれる会社に育てる。
そのすぐ後、スタッフの半分が一気に会社を辞める事態になり「自分を変えなければ」と発起しNLPや心理学を本気で学ぶ。
『過去と他人は変えられないが、自分と未来は変えられる』ことを知り、全国の経営者やビジネスパーソンにもそれを伝えるため、セミナー活動や研修活動をしている。
【保持資格】
全米NLP トレーナー・LABプロファイル®トレーナー
交流分析士・心理カウンセラー・行動心理士